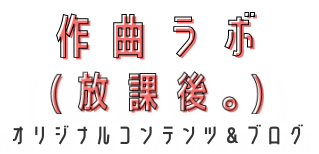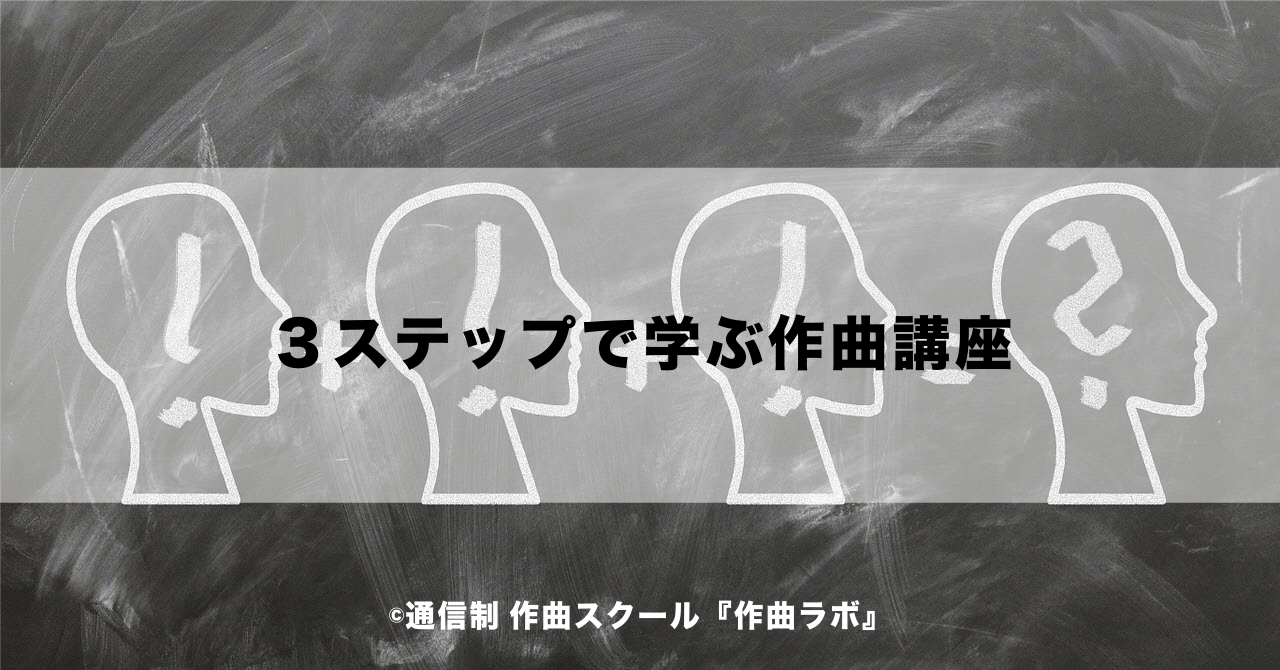「作曲って難しそう」とか「作曲なんてできるわけがない!!」と思っている方の大半は、そもそも「作曲ってどうやってするかわからない」、あるいは「作曲の手順がわからない」というのが大きな理由だと思います。
ここでは3つのステップで実際に作曲の流れを見ていきます。
まずは「音楽の三大要素」を理解しよう

そもそも”音楽”って何をもって音楽になるのかというと、大きく分けて次の3つです。
- メロディ
- リズム
- ハーモニー
「メロディ」は音楽のメインパートで、その音楽の主張部分になります。リスナーの耳に届きやすいため、音楽の中で一番強く印象を残すところです。
「リズム」は音楽の骨格に当たるものです。リズムがあることで、強弱のポイント、テンポ(速さ)、また区切り(小節)が決まります。
「ハーモニー」は和音の流れのことです。音楽に広がりがあるのはバックでコード(和音)が鳴らされているためで、これをどういう流れにするかで喜怒哀楽を表現することができます。
ということで、ざっくり言うと作曲というのは・・・
- メロディを考える
- リズムを決める
- ハーモニーを考える
という3つのステップに分けられます。まずはこの3つの軸を作ることを優先させていきます。

どこから作ってもOK、ただし・・・

「メロディを考える」「リズムを決める」「ハーモニーを考える」のステップは人によって、また場合によってそれぞれで、こうすべきという決まった流れはありません。
ただ、個人的には・・・
- リズムを決める
- ハーモニーを考える
- メロディを考える
という手順に沿って作るのがおすすめです。
※ハーモニー(コード進行)に詳しい方は「ハーモニーを考える」を最初に行っても良いです
リズムとハーモニーはいわばパズルの枠みたいなもので、この2つで音楽の全体像がほとんど決まるといっても過言ではありません。ですので、メロディも作りやすくなります。
一方、メロディから作るのはある程度の作曲経験がない方にはおすすめできません。それについては下記を参考にしてみてください。
実際に作曲してみよう!
では実際に次の3ステップに沿って作曲していきましょう!
ステップ1:リズムを決める

冒頭でもお伝えしたように、リズムは音楽の土台にあたる部分です。
同じハーモニー・メロディであっても、リズムが変わることで全く異なる音楽にしてしまうことがあります。
極論を言えば、「リズム(ドラム)=音楽」といっても良いくらいです。
しかし、「リズムの知識なんてない!」「打楽器なんか弾いたことがない!」という方もいらっしゃるでしょう。
そういう方は「ループ素材」を使いましょう。
「ループ素材」というのは、1〜4小節程度の短い音素材集のことです。ほとんどの場合が、実際の生演奏を録音したものですので、このループ素材を使うことによってかなりのリアル感が出てきます。
「自分はプロを目指しているので、そんな音素材なんて使いたくない!!」「そんな”出来合い”のものを使って作曲するなんて素人がすることだ!」と思ったあなた・・・
実は、こういった音素材はプロの方も積極的に使われています。むしろプロの人の方が使っていると言っても過言ではありません。
ちなみに、「ヒップホップ」という音楽のジャンルは、ループ素材や音素材をあれこれいじっている時に生まれた音楽です。
では何種類かループ素材を取り上げてみましょう。
【Pops・Rock系ドラムループ】
【Jazz系ドラムループ】
【Blues系ドラムループ】
【R&B系ドラムループ】
【Funk系ドラムループ】
【Dance系ドラムループ】
【南国系ドラムループ】
こういったドラムループ集の中から自分の目的(作りたい曲・ジャンル)にあったものを選択していきます。
なにもイチから作り上げる必要はありません。
ループ素材は今ではほとんどのDAW(作曲ソフト)に付属しているので、最初はそれを使ってみましょう。
付属のループ素材では物足りないなと感じましたら市販のものを手に入れても良いかもしれません。
ジャンル別になっているものから、いろんなジャンルをまとめたものまで多種多様ありますので色々探してみてください。

ステップ2:ハーモニーを考える

リズム(ドラムループ)が決まったら今度はハーモニーです。
ハーモニーでは「コード(和音)」の知識が必要になってきます。
コードについてご存じのない方は下記で極力わかりやすくコードについて解説していますので、ご覧いただければと思います。
ここでは上記ページ内の、例4「②→⑤→①→⑥→②→⑤→①」というハーモニー(コード進行)を使います。
この状態だとただ和音が鳴っただけという感じですが、ステップ1のリズム(ドラム)を合わせてみます。
そうすると「曲っぽさ」がグッと出てきます。とりあえずステップ1の「Pops・Rock系ドラム」を加えてみましょう。
【コード進行例4+Pops・Rock系ドラム】
※コード進行のテンポはドラムにあわせています
では、今度は同じコード進行に前回の「R&B系ドラム」を付け加えてみましょう。
【コード進行例4+R&B系ドラム】
※コード進行のテンポはドラムにあわせています
では、今度は同じコード進行に前回の「Dance系ドラム」を付け加えてみましょう。
【コード進行例4+Dance系ドラム】
※コード進行のテンポはドラムにあわせています
どうでしたか?「コード+ドラム(リズム)」でかなり曲っぽさが出てきたでしょう。
しかも同じコード進行(伴奏)であっても、ドラムを変えるだけでかなり雰囲気も変わっていくのがわかるのではないでしょうか?
プロの方でも同じ方法で作曲をしていきます。

ステップ3:メロディを考える

リズム(ドラム)とハーモニー(コード進行)を合わせたものにメロディをつけると「音楽」の完成です。
これまでのドラムループやハーモニーとは違って、メロディには著作権があるため、誰かが作ったものを拝借するということができません(たとえ作った本人であっても同じメロディを別の作品に二次利用することはほとんどありません)。
ですので、画一的にこうやっておけばOKというものはありません。

ですので、自分なりに心地よい流れを模索しながら作っていきます。
ここでは最もオーソドックスな方法でメロディを作っていきましょう。
その方法とは・・・「鼻歌」です。
前回までの自作のカラオケに「フフン♪〜」と鼻歌でメロディを探っていきます。
鼻歌の作り方で効果的なものが、「始まりの音をあらかじめ決めて」おいて、「その音を軸に鼻歌を練っていく」というのがあります。一度お試しください。
例として、カラオケを聴きながら次のような鼻歌メロディを考えました。
では、ステップ2までで作ったカラオケにこの鼻歌メロディを付け加えてみましょう。
【Pops・Rock系カラオケ+鼻歌メロディ】
【R&B系カラオケ+鼻歌メロディ】
【Dance系カラオケ+鼻歌メロディ】
同じ方法で、Aメロ・Bメロ・サビという風にセクションを積み上げて、1曲が完成していきます。
完成後はアレンジで

以上の3ステップで作曲は完成です。完成後は作曲ではなく、「アレンジ(編曲)」になります。
アレンジですることは、ベースやストリングス(弦楽器)など他の楽器を加えたり、コードやメロディをより自分のイメージに合ったものに変更したりします。
つまり、より曲らしく変身させる作業です。そういう意味では「アレンジ」は女性のお化粧みたいなものです。
ボトムス(ドラム)やトップス(コード)、髪型(メロディ)など完成させて、最終的に化粧(アレンジ)で終わりということです。
※人によっては順番が違うかもしれませんが・・・

終わりに
以上、作曲作業の流れを見ていただきましたが、作曲は基本的に毎回同じような流れで行います。
ある程度作曲の実績を積んでいくと、だんだんと自分の中で作曲の流れが「マニュアル化」されていき、自分なりの「コツ」が掴めるようになっていきます。
そのため、最初は1曲作るのに2〜3週間かかっていたものが、曲数を重ねるごとに徐々に日数も短くなってきます。
つまり、作曲はすればするほど「質」「量」「時間」ともに向上していきます。
ここが「作曲のおもしろいところ」です。自分の進歩を「作曲を通して」実感できるんですから。

また、かなり慣れてくると、次のような鼻歌を・・・・
次のようにアレンジまですることが可能になります。
もちろん一朝一夕で誰でも簡単にとはいかないのも事実です。
クオリティの向上のためには、音楽を多く聴いたり、基本構造である「音楽理論」を身につけていくことも必要になってきます。
以上「3ステップで学ぶ作曲講座 」でした。ご参考になりましたら幸いです。